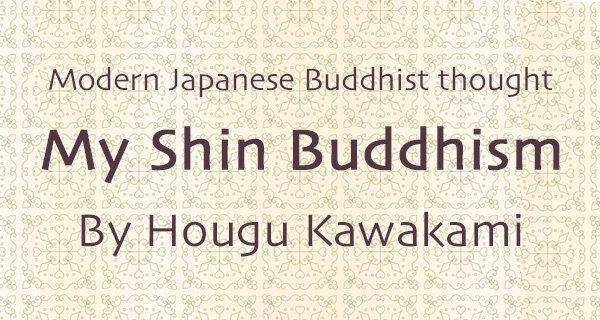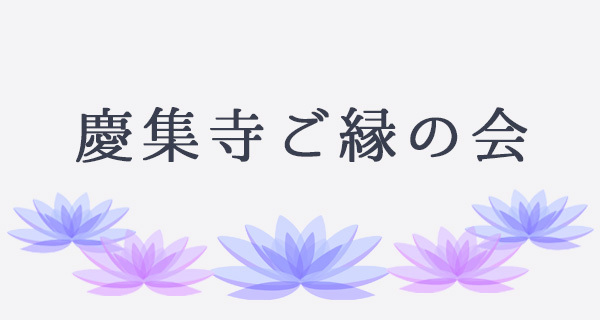私が慶集寺に入って僧侶としての生活を始めた29歳のときから四半世紀が過ぎて、これまで一緒にお参りしてきた方々とのお別れが、ずいぶん多くなりました。
毎月ご自宅にお伺いして、仏壇の阿弥陀さまに向かって一緒にお参りをして、いろんなお話をさせていただいてきた方々とのお別れです。
まだ若かった頃は、人が歳をとって亡くなるのは仕方がないことだと、割り切って考えることができた気がします。けれども、深いご縁を感じざるを得ないような関係にまでなると、家族同様にとは言いませんが、とても辛く悲しく寂しい気持ちになります。
導師という立場にあるものとしては、粛々とご葬儀をお勤めしなければいけないのですが、胸が詰まってお経が読めなくなるようなときもあります。
出遇いがあれば、必ず別れも訪れるのが人生です。
親しい人との死別を、誰もが、どうしようもなく、経験しなければいけないのです。
どれだけ悲しみに暮れていても、ご遺体をそのままにしておくわけにはいきません。旧来からの慣習に従ってお通夜・ご葬儀をお勤めし、火葬という流れになるのが世の習いです。
どんなひとでも生前中は自分の意思をもって、それぞれのこだわりがあって生きてこられたはずですが、お葬式は大体にして世間的な流れに沿って進行し、荼毘に付されてご遺骨になられます。
ご遺族にとっては、まだ生前中のお姿が鮮明な記憶として残されているなかで、亡くなられたことの現実を、なかなか受け入れることができないというのは、当然のことだと思います。
いつものように家に帰ってくるんじゃないか、また連絡がくるんじゃないか、まだどこかにいるんじゃないか。そういう思いを持たれるのは、自然な心情だと思います。
天国なのか何処なのかはわかりませんが、もう亡くなられた方が、いまはどこでどんなふうにしているのだろうかと、ふと思うこともあるでしょう。
いろんなひとが、まことしやかに自分の想像する死後について語られることを聞きますが、本当のところそれは生きてるかぎり、誰にも分からないことでしょう。どれだけ高名な科学者や哲学者や、宗教者が自説を述べられたとしても、全ての人を納得させられることはないはずです。
ご葬儀やご法事のときに、もっともそうに語られる法話にしても、なかなか受け入れられることばかりではないことは承知しています。それでも私は僧侶として、自分自身が確かに信じていることを、ご遺族やご縁の方々にお伝えしなければいけないと思っています。
古来より日本では、亡くなられた人は「ほとけになる」と言い習わされてきました。
仏に成ると書いて、成仏(じょうぶつ)です。
肉体がある人間として自分自身を生きている間は、
自分本位・自己中心の「我執」にしがみついて生きざるを得ない私たちですが、
我をほどいて、仏と成って、
ほどいて、ほとけて、ほとけとなって、成仏されるのです。
自分自身が信じることを、ご縁の方々に伝えていくしかありません。導師の役を務める者として、亡くなられた方は必ず「成仏」されていると、私はいつもお伝えしています。
仏の存在や亡くなられた方々の成仏を、信じるも信じないも、ひとそれぞれの自由だと思います。けれども、私たち一人ひとりが、願われて生かされているということだけは、信じるべきことです。
亡くなられた方々は、自らの肉体や存在の執われから自由になって、解き放たれて、いまはもう私たち一人ひとりのことを、一心に願ってくださっていると、信じなければいけません。
自分自身のこだわりを脱ぎ捨てて、今はもう願いそのものとなって、私たちを見守ってくれています。