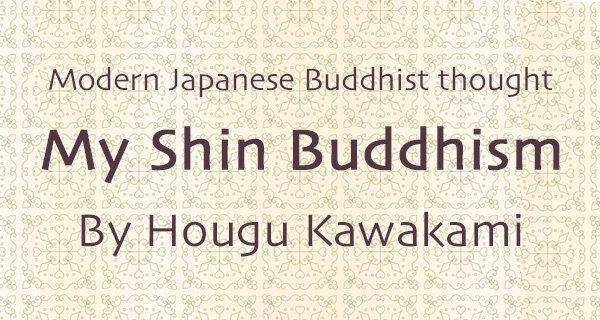ブッダといえば仏教の信仰対象を指す用語という認識が、現代では一般的であるように思われます。しかしながらゴータマ・ブッダの生存された古代インドの時代に立ち返ってみると、必ずしもそれは仏教固有のものではなかったようです。
仏教学者の並川孝儀氏が著された『ブッダたちの仏教(ちくま新書 2017年)』には、
「ブッダ(buddha)」という語は、仏教で初めて現れる用語ではなく、すでにインドの聖典『ヴェーダ』や『ウパニシャッド』、叙事詩『マハーバーラタ』に「真理を悟った人」という意味で用いられており、仏教と同時代のジャイナ教の古い聖典などにも聖者や賢者などの呼称として使われていた。
という記述があります。「ブッダ(覚者)」という用語は、必ずしも仏教のみに用いられたものではなく、インドの宗教世界全般において重要な概念である「ダルマ(法・真理)」に基づき広く用いられる、極めて一般的な呼称だったというのです。
また同書には、
ゴータマ・ブッダは「ブッダたちの中で最高のゴータマ」(『スッタニパータ』三八三偈など)と表現されている例がみられるが、これもゴータマ・ブッダ以外にもブッダと呼称されていた者が存在していたことを示している。
という記述もあります。これは、ゴータマ・ブッダによって説かれた「ダルマの教え」を聞き学び、それを修得して同様にブッダ(目覚めたる者)となった人々が、他にも複数存在したことを意味しています。そして、複数形で「ブッダたち」と称される集合の中にある「最高のブッダ」として、ゴータマ・ブッダが存在していたということです。
続く一文には、
[”ブッダ”という用語には]仏教修行者が複数形で用いられている例がある。その一例は、「(ゴータマ・ブッダに)従って悟ったひと(アヌブッダ)」という表現で、仏弟子マハーカッサパ(大迦葉)やアンニャー・コンダンニャを指しているものである。これらの仏弟子はゴータマ・ブッダの直弟子なので、「アヌ(に従って)」という接頭辞が付けられてはいるのは当然であるが、何よりも彼らもブッダと呼称されていた用例であることに留意しておく必要はあろう。[中略]仏教の起こった当初はすぐれた仏弟子もブッダと呼ばれて普通名詞として使われていたものが、後になって何らかの理由でブッダは唯一となり、固有名詞としてのゴータマ・ブッダが誕生していく経緯が読み取れるのである。
とあります。
「ブッダたちの中で最高のゴータマ」と称され、その人の説かれた「ダルマ」が、時空を超えて伝わり得る普遍的な真実性のあるものだったがゆえに、ブッダといえば「ゴータマ・ブッダ」となり、それがやがては固有名詞として見なされるまでになったということです。
先の引用文中にある「アンニャー・コンダンニャ」とは、ゴータマ・ブッダが悟りを開かれた後、最初に教えを説いた五人の修行者のなかの一人の名前です。この人が五人のなかで一番最初にブッダが説かれたダルマ(仏法)を理解されたので、当時のインドの言葉で「アンニャー(理解した!)」と、ブッダは感嘆の声を挙げられたと伝えられています。このことから「コンダンニャは悟った!」という感嘆の言葉が、そのままこの仏弟子の通称になったと言われています。
このエピソードから、ブッダが認めたブッダがいたということがわかるでしょう。ゴータマ・ブッダによって言語化された「ダルマ(法・真理)」が、ゴータマ以外の人々にも響き伝わり理解され、共有されたことがここからも読み取られます。
ブッダとはダルマに目覚めた存在です。そしてその真理の法が、他者にも同じく認識され共有されることによって、同様にブッダとなった人たちが、ゴータマの他にも現れ続けたということです。
「過去七仏」(釈尊の前にダルマに目覚められた存在が6人いた)という信仰が仏教には極めて古い時代からあったといわれるように、目覚め、気付き、悟られるべきダルマがどの時代にも必ずあるということは、どんな時代であってもそれに目覚め、気付き、悟るブッダが必ず現れ得るということに、理論的にはなるのです。
ブッダが説かれたダルマを自ら修得した「アヌブッダ(ゴータマに従って目覚めたひと)」が、自らの悟ったダルマを自身の言葉として語る際には、その現場となる地域や時代や文化などの背景に応じたものとなるはずです。そしてそれは、状況に応じて多様に表現されるはずなのです。
ゴータマ・ブッダ滅後約2500年の間に世界の各地に伝わり広がっていった仏教は、それぞれの地域文化と混交しつつ、その時々に現れた「アヌブッダ」によって多様に展開していった。そんな道筋を想像することが出来そうです。
 photograph: Kenji Ishiguro
photograph: Kenji Ishiguro